
「進研ゼミを始めたけど、続けるのが大変…」
「やる気がなくて、溜めちゃうから辞めたいかも」
我が家も本当にそうでした。
最初は「ちゃんと全部やらせなきゃ」と思って、つい口うるさくなり、子どもも嫌がって続かなくなって…。
何度も失敗して、親子でケンカしたこともたくさんあります。
でも、そうやってつまずく中で
「このままじゃ続かない。親の関わり方を変えないと」と気づきました。
完璧にはできなかったけど、少しずつ「子どもの年齢や気持ちに合わせて関わり方を変える」ことを意識したら、親子ともに少し楽になって、続けやすくなったと思います。
ここでは、我が家のそんな失敗と試行錯誤から「こう変えたら良かったな」「これが役立ったな」と感じた学年別の進め方をまとめました。
同じように悩む方のヒントになれば嬉しいです。

【1・2年生】勉強の楽しさを育てる「親子時間」
1・2年生の頃は、まだ勉強が「遊びの延長」であってほしい時期。
でも当時の私は「ちゃんとやらせたい」という気持ちが強くて、つい「早くやって!」と急かしたりしてしまいました。
そのたびに子どもは不機嫌になり、泣いたり嫌がったり…。
そんな失敗を重ねる中で「これは逆効果だな」と気づき、少しずつ
「一緒に楽しむ」ことを意識するようにしました。
進研ゼミをやるときも
– 隣に座って一緒に問題を読む
– できたらしっかり目を見て「すごい!」と褒める
– 分からなくても「一緒に考えよう」と声をかける
親子で「なるほどね」「楽しいね」と会話する時間を大事にしたら、子どもも嫌がらずに取り組む日が増えたと思います。
進研ゼミはイラストや解説が分かりやすいので、こうやって「一緒に楽しむ」にはすごく使いやすかったです。
この時期は勉強というより、分かると楽しい!というような感覚を大切にすると勉強嫌いになりにくいかと思います。

【3・4年生】ギャングエイジの難しさを受け止める
3・4年生は本当に難しかったです。
「ギャングエイジ」と呼ばれる時期で、イライラしたり反抗したり。
「もう勝手にしなさい!」と私も感情的に言ってしまうことが増えました。
でもそのたびに親子関係がぎくしゃくして、勉強どころじゃなくなって…。
その経験から「無理にやらせても意味がないな」と感じて、少しずつ関わり方を変えるようにしました。
意識したのは
– 進まない日があっても「そういう日もあるよ」と受け止める
– 無理にやらせず「今日はどうする?」と子どもと相談する
– 少しでも進めたら「頑張ったね!」とちゃんと喜ぶ
進研ゼミも溜まることはありましたが、「全部やれ」じゃなく「ちょっとでもOK」に気持ちを切り替えたら、子どもも少しずつ話をしてくれるようになった気がします。
この時期は「親は味方だ」「失敗しても大丈夫」という安心感を持たせることが本当に大事だったなと今でも思います。
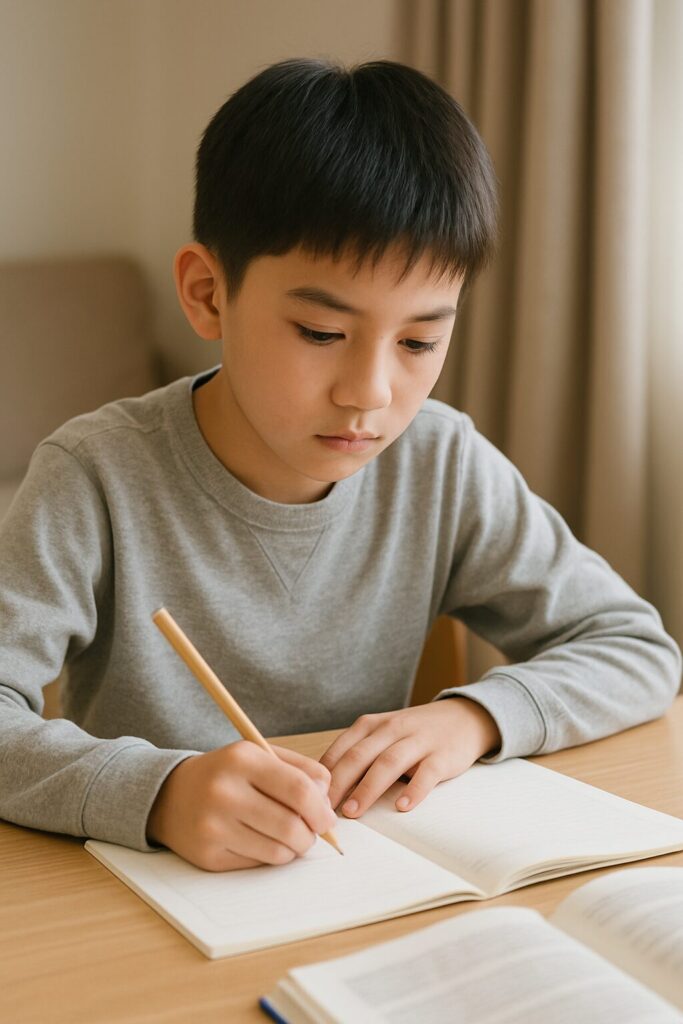
【5・6年生】自立心を尊重して「任せる力」を育てる
5・6年生になると、ぐっと大人っぽくなってきます。
でも親としては「やってるのかな?」と心配で、つい口出ししたくなる時期でもありました。
私も「ちゃんとやったの?」「なんでやってないの?」と聞きすぎて嫌がられることが増え…。
そのたびに関係がこじれてしまった反省があります。
そこから「もう少し任せてみよう」と意識を変えて、少しずつ
– 「どう進める?」を子どもに決めさせる
– 親は口を出すより「見守る」
– 終わったら「どうだった?」と言いながら感想を聞く
-「頑張ったね」と声をかけてあげる
こんな関わり方を試すようにしました。
もちろんサボりたい日もあるけど、「全部やりなさい!」より「今日はどこまでやる?」と相談する方が、お互いイライラしないで進められたなと思います。
進研ゼミは自分のペースで進められるので、親が「見守る役」に回る練習をするにはすごく良かったです。
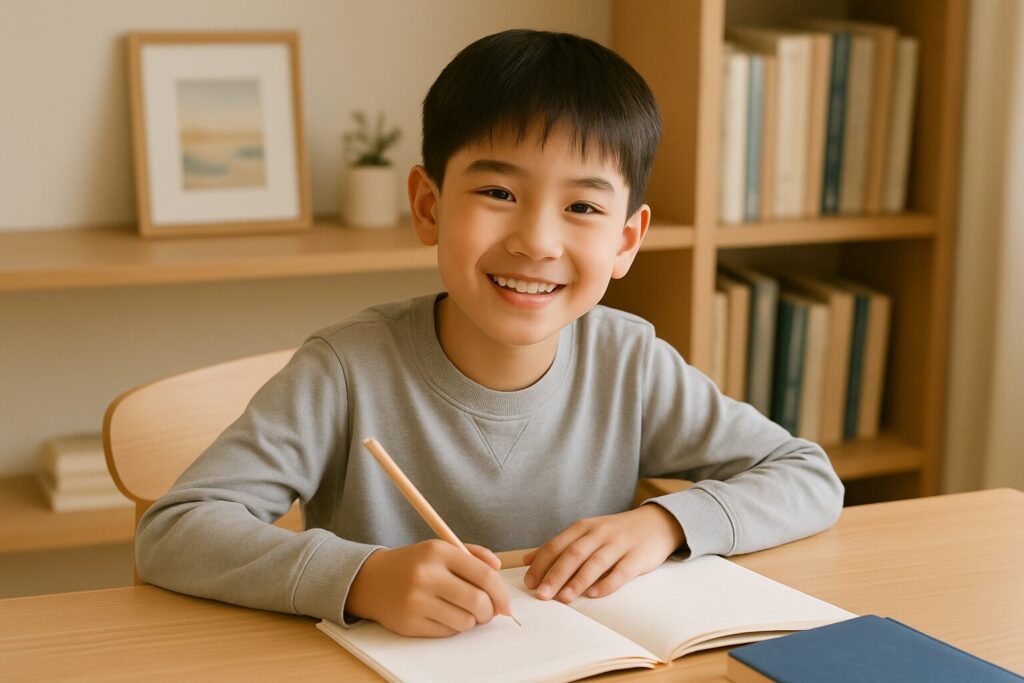
■進研ゼミを辞めたくなるときも、続けるコツは「完璧を求めない」
正直、進研ゼミは「溜める」ことも多かったです。
我が家も「どう続けるか何度も話し合いながら工夫してきました。」
でも、「全部完璧にやるのは無理なんだ」と考えを変えてからは、気持ちがずいぶん楽になりました。
– 100%やることを目標にしない
– 10%でも20%でもやれたら上等
– 親子で「少しでもできたね」と喜ぶ
こうやって少しハードルを下げたら、子どももプレッシャーを感じにくくなったし、私も「やらせなきゃ!」のイライラが減った気がします。
進研ゼミの良さは「家庭学習を習慣にするきっかけをくれること」だと思います。
塾だと送り迎えも大変だし、様子も分かりにくい。
家で親がそばで見守り、声をかけながら進められるのは大きなメリットだと今は感じます。
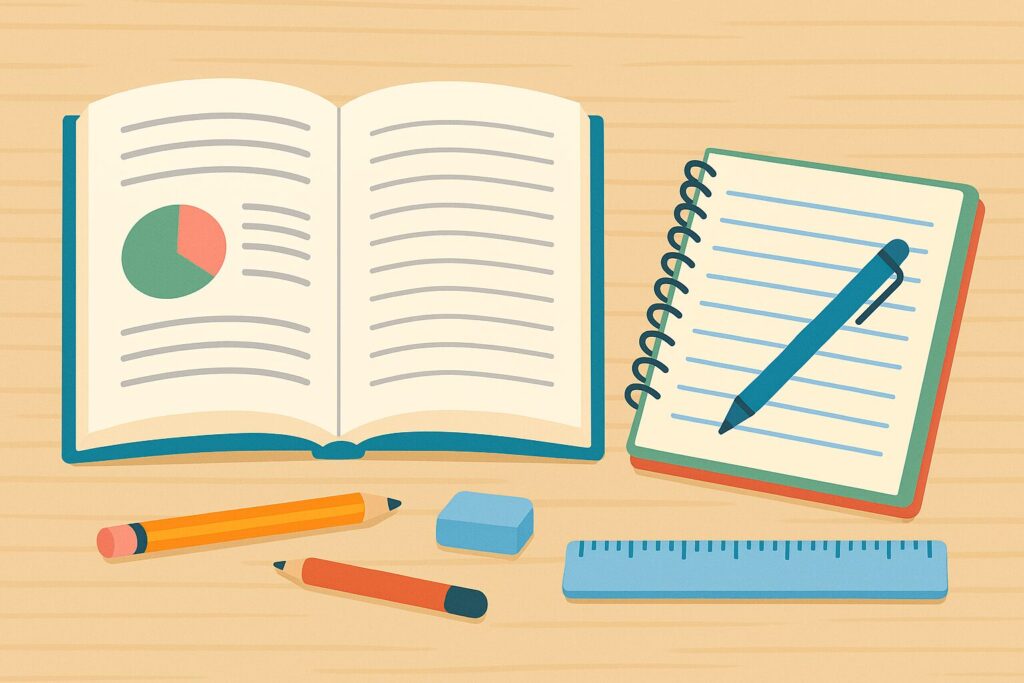
■まとめ:子どものペースを尊重しながら家庭学習を習慣化しよう
進研ゼミを続けるコツは、「年齢に合わせて親の関わり方を変えること」だと本当に感じます。
– 低学年は「親子で一緒に楽しむ」
– 中学年は「見守る、寄り添う」
– 高学年は「任せる、尊重する」
そして「完璧を求めない」。
中学生になると、自分で学習する力がとても大切になります。小学生のうちはその土台を作る時間。そうしておけば、中学でもスムーズに学習を進めやすくなると思います。
進研ゼミは子ども一人ひとりのペースで進められるからこそ、親も子どもも無理なく続けやすいです。
家庭学習を習慣にする一歩として、本当におすすめだと今は思っています。
同じように「どうしたらいいんだろう」と悩む方が、少しでも気持ちを楽にして進められるヒントになれば嬉しいです。
まずは資料請求をして、お子さんに合うかじっくり検討してみてください。


